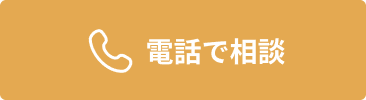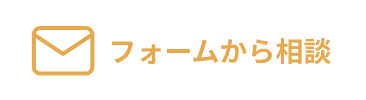更新日:2024.05.24
公開日:2024/5/9
会社設立前後でどんな融資が受けられる?成功する会社設立を解説!


StarMember公認会計士・税理士事務所
代表 山田俊輔(公認会計士・税理士・経営心理士)
あずさ監査法人にて、東証一部上場企業の会計監査、上場準備会社の監査、会社買収時のデューデリジェンス業務等を担当。
2010年に独立開業し、Star Member (スタメン)公認会計士・税理士事務所と株式会社日本会計サービスを立ち上げ、連結売上1,000億円超の社外取締役や売上数百億円~数億円の会社の取締役、監査役などを務める。2017年には野村證券なんば支店アドバイザリーボードメンバーにも選任。
「会社設立前後にどのような融資が受けられるのだろうか?」
「地方自治体などが提供する融資にはどのようなものがあるのか?」
このような悩みをお持ちではないでしょうか。
会社設立の際に多くの方が直面する問題には「資金調達」があげられます。
創業時に融資を受けられるかどうかによって、設立後の経営方針の幅が大きく変わってきます。
ここでは、「会社設立前後にどのような融資が受けられるか」について詳しく解説します。
会社設立をご検討の方は、ぜひ最後までお付き合いください。
1.会社設立時には日本政策金融公庫の創業支援の融資と制度融資を受ける事業者が多い
会社設立の際に受ける融資(創業融資)は銀行など、民間の金融機関でも対応していますが、新しい事業を始める場合は実績がないため、融資を受けることが難しい傾向にあります。
もちろん、しっかりとした事業計画書や資金繰り表を作成することにより、銀行などの審査を通過することもできますが、決して簡単なことではありません。
そこで、創業時に限定して融資を受けることができる「公的創業融資」を検討してみましょう。
公的創業融資とは、政府系の金融機関(日本政策金融公庫)や地方自治体などが提供する創業融資(制度融資)のことであり、会社設立後の資金繰りをサポートする融資制度です。
会社の営業実績がなくても融資を受けることができるため、創業時の強い味方になるでしょう。
日本政策金融公庫や制度融資の目的は、営利を求めるものではなく、国や地域の経済発展を支えることです。
そのため、低金利・無保証など、事業者にとって有利な条件で融資を行っており、多くの事業者が創業時の資金調達に活用しています。
1-1.日本政策金融公庫の創業支援の融資の特徴
日本政策金融公庫の事業には「国民生活事業」があり、国民生活事業の1つとして小規模の事業者や会社設立前後の会社を対象とした創業支援の融資を行っています。
創業支援の融資には「新規開業資金(新企業育成貸付)」や「女性、若者/シニア起業家支援」などがあり、柔軟な審査を行う低金利の融資があります。
創業融資は日本政策金融公庫の得意としている分野でもあるため、銀行の融資が受けられない場合であっても融資を受けられる可能性があります。
1-2.地方自治体などが提供している制度融資の特徴
制度融資は、地方自治体と金融機関や信用保証協会が協力して提供している融資のことを言います。
地方自治体によって提供している融資の内容は異なりますが、基本的には金融機関が保証協会へ保証を依頼し、本来は融資を受けた会社が全額負担しなければならない保証料の全部、または一部を地方自治体が補助してくれる制度になります。
制度融資では、金融機関の貸付原資の一部を地方自治体が負担しているため、低金利での融資が可能となっています。
また、保証協会の保証もあるため、融資の審査のハードルも高くありません。
2.会社設立前後に受けられる融資
会社設立前後に受けられる融資には次のようなものがあります。
【日本政策金融公庫の創業融資】
| 融資制度 | 対象者 | 融資限度額 | 金利 |
| 新創業融資制度
|
新しく事業を開始する方や事業開始後2期間以内 | 3,000万円
(運転資金1,500万円) |
基準金利2.4~3.5%
※無担保、無保証人での融資は他の制度と組み合わせる必要がある |
| 新規開業資金 | 新しく事業を開始する方や事業を始めておおむね7年以内の方 | 7,200万円
(運転資金4,800万円) |
基準金利1.1~3.2%
(担保の有無で異なる) |
| 女性、若者/シニア起業家支援資金 | 新しく事業を開始する方や事業を始めておおむね7年以内の方のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方 | 7,200万円
(運転資金4,800万円) |
特別利率A0.7~2.8%
(担保の有無で異なる)
|
| 再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資) | 新しく事業を開始する方や事業を始めておおむね7年以内の方で廃業歴がある方 | 7,200万円
(運転資金4,800万円) |
基準利率1.2%(5年以内)
貸付期間や要件によって異なる |
| 新事業活動促進資金 | 経営革新計画の承認を受けた方など | 7,200万円
(運転資金4,800万円) |
要件によって特別利率が異なる |
| 中小企業経営力強化資金 | 認定経営革新等支援機関を通じて経営革新などを行う方、「中小企業の会計に関する指針」に従った会計処理を行う方 | 7,200万円
(運転資金4,800万円) |
特別利率A0.7~2.8%
(担保の有無で異なる) |
【地方自治体の制度融資(大阪府)】
| 融資制度 | 対象者 | 融資限度額 | 金利 |
| 開業サポート資金(開業資金・地域支援ネットワーク型) | 事業開始準備を行っている方、事業開始から日が浅い方 | 3,500万円 | 固定金利1.2~1.4%(要件により異なる)
信用保証料0.5~1% ※各地方自治体に利子補給・保証料補助制度がある |
2-1.日本政策金融公庫の創業融資
日本政策金融公庫の創業融資の中でも「新創業融資制度」「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家支援資金」の3つが利用しやすい制度になります。
各制度の特徴を見ていきましょう。
2-1-1.新創業融資制度の特徴
新創業融資制度は「新たに事業を始める方、事業開始後間もない方(税務申告が2期間以内)」を対象とした融資制度です。
融資限度額は、設備投資に利用する場合は3,000万円、創業後の運転資金に利用する場合は1,500万円までになります。
新創業融資制度の特徴は「無担保、無保証で融資を受けることができる」ことです。
代表者個人が連帯保証人になる必要もないため、融資を申し込むハードルが下がります。
ただし、新創業融資制度は単独で利用することはできません。
新規開業資金や女性、若者/シニア起業家支援資金などの他の融資制度と組み合わせて併用することになります。
イメージとしては、「新創業融資制度を併用することで無担保、無保証をオプションとして付けることができる制度」と考えておくといいでしょう。
新創業融資制度のデメリットは、融資限度額が他の融資と比較して低いことです。
新創業融資制度と他の融資制度を併用した場合、無担保、無保証になりますが、融資限度額が新創業融資制度に準じることになります。
例えば、新創業融資制度と新規開業資金を併用した場合の融資限度額は3,000万円(そのうち運転資金1,500万円)になります。
新規開業資金を単独で利用した場合は7,200万円(そのうち運転資金4,800万円)が融資限度額になりますので、利用を検討する場合には融資限度額に注意しましょう。
また、新創業融資制度には「自己資金要件」があります。新しく事業を始める方(事業開始後1期間以内)については、「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」が必要です。
2-1-2.新規開業資金の特徴
新規開業資金は「新しく事業を始める方や事業開始後間もない方」が対象です。
新創業融資制度の場合は「事業開始後2期間」であるのに対し、新規開業資金は「事業開始後おおむね7年以内の方」が対象です。
新規開業資金の融資限度額は「7,200万円(うち運転資金4,800万円)」となっており、新創業融資制度よりも高いことが特徴です。
ただし、新規開業資金には、原則的に担保、保証人が必要になります。新創業融資制度を併用することで無担保、無保証で融資をうけることができますが、融資限度額が新創業融資制度に準じるため低くなってしまうデメリットもあります。
金利については、Uターン等で地方で新しく事業を始めるなど、一定の要件を満たすことで特別利率が適用されます。
利用できる要件があれば金利が低くなりますので、確認してみましょう。
2-1-3.女性、若者/シニア起業家支援資金の特徴
女性、若者/シニア起業家支援資金は、新規開業資金と同様の融資制度で「女性または35歳未満か55歳以上」の場合であれば、低い金利で融資を受けることができる制度です。
原則的に無担保、無保証ですが、担保や保証人を設定することで、さらに金利を下げることが可能です。
2-1-4.再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)の特徴
再挑戦支援資金(再チャレンジ支援資金)は、一度廃業していても利用することができる融資制度です。
おおよそ7年以内に廃業した経験がある方が対象になっており、廃業するに至った経緯ややむを得ない理由、廃業を新規事業にどう活かしていけるのかなどを踏まえた事業計画が必要です。
融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)になっており、金利は基準金利に準じて適用されます。
担保、保証人については、原則的に必要です。
2-1-5.新事業活動促進資金の特徴
新事業活動促進資金は、主に新事業を立ち上げる時に利用される制度です。
「新たに事業を始める方」以外であっても融資を受けることができるため、創業時は新規開業資金で融資を受け、事業拡大時に新事業活動促進資金を受けるといった資金調達が可能です。
2-1-6.中小企業経営力強化資金
中小企業経営力強化資金は、新たに事業を始める方を対象とした融資制度です。
新規開業資金よりも金利が低く設定されていることが特徴です。
融資限度額は、新規開業資金と同様に7,200万円(うち運転資金4,800万円)ですが、認定経営革新等支援機関を通じて経営革新などを行うことや「中小企業の会計に関する指針」に従った会計処理を行うことなどの要件があり、新規開業資金よりも要件が厳しくなっています。
2-2.地方自治体の制度融資
地方自治体の制度融資は、地方自治体によって融資の要件が異なります。
基本的には、低金利で長期間の融資に対応しており、融資審査のハードルも高くはありません。
制度融資は、地方自治体の窓口で相談する必要がありますので、事業を行う場所の地方自治体がどのような制度融資を提供しているのかを確認してみましょう。
大阪府を例にあげると、融資限度額3,500万円の「開業サポート資金(開業資金・地域支援ネットワーク型)」があります。
金利は固定金利で1.2~1.4%、信用保証料0.5~1%になっています。
各市町村で利子補給金や保証料補助制度がある場合がありますので、窓口で確認してみましょう。
3.会社設立時に融資を受ける際の注意点
会社設立時に初めて融資を受ける場合には、どうしても不安になってしまうと思います。
融資に失敗しないために次の点に注意して創業融資を検討しましょう。
- 融資には審査がある
- 遅延や滞納をしない
- 希望額の融資が得られるとは限らない
3-1.融資には審査がある
日本政策金融公庫の融資や制度融資は、申し込めば誰でも融資が受けられるのではなく、審査を通過することで初めて融資を受けることができます。
現実的な事業計画書を作成し、融資を受けた資金の使用用途を明確にし、確実な返済計画を提示することで審査が通りやすくなりますので、説得力のある資料作りと明確な説明ができるように準備しましょう。
3-2.遅延や滞納をしない
融資審査では、個人の信用度も重要になってきます。過去にローンや税金などの支払いに遅延や滞納があると融資審査に通りにくくなってしまうこともありますので、会社設立前であっても遅延や滞納がないように気を付けましょう。
3-3.希望額の融資が得られるとは限らない
融資審査に通っても、希望額が融資されるとは限りません。
融資審査時に「なぜその額が必要なのか」についての根拠を提示し、説明することが重要です。
また、融資審査で必要額の根拠を示したとしても、金融機関には「支店決裁権」というものがあるため、希望額の融資を受けられない場合もあります。
このことを踏まえたうえで事業計画を考えるようにしましょう。
まとめ
創業融資を受けられるかどうかは、設立後の会社の事業を左右する最も大切なことの1つです。
「日本政策金融公庫と制度融資のどちらを利用した方がいいのか」「審査が通るためには何を準備した方がいいのか」など、創業融資を検討する場合は入念に確認しましょう。
Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所では、会社設立の際の融資についてのご相談も承っております。
初めての融資申し込みで不安を抱えている方はぜひ、当事務所までご相談ください。
これからの事業について一緒に考え、併走していけるパートナーとしてサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。